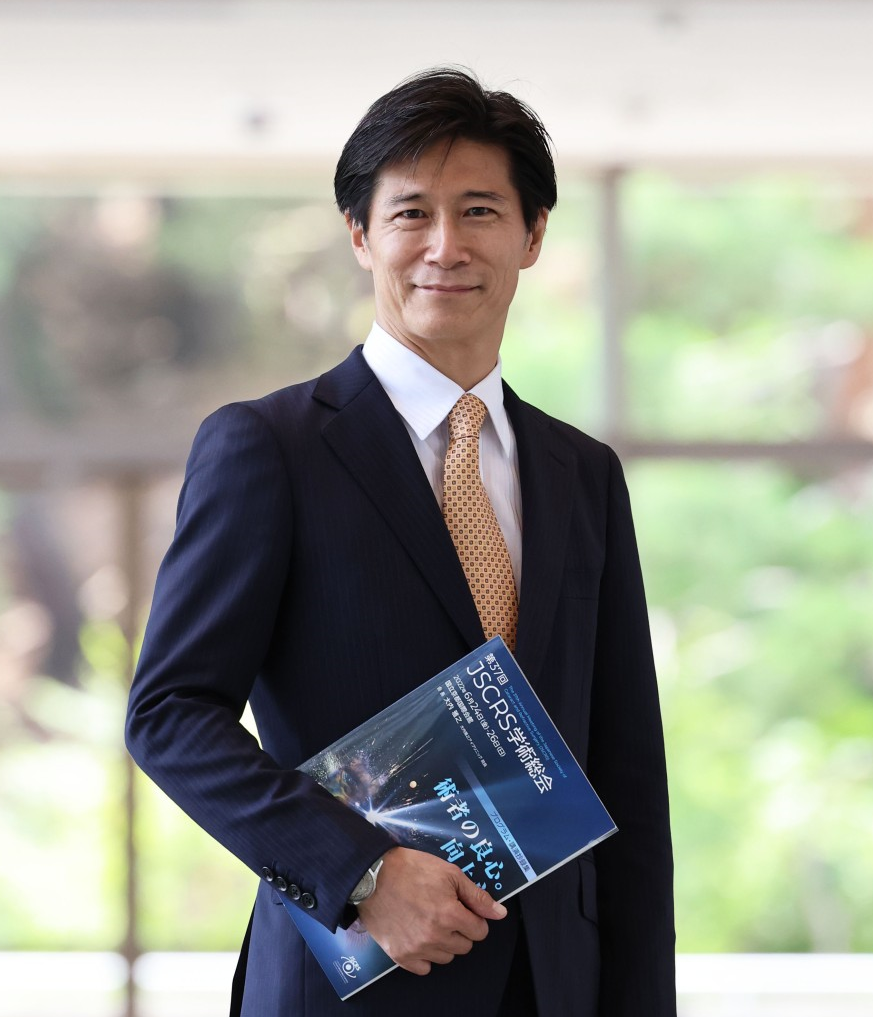白内障の手術を勧められたとき、多くの人が最初に気になるのは「費用はいくらかかるのか」という点でしょう。
保険が適用される範囲や自由診療との違い、レンズの種類による差、公的制度の活用可否など、知っておくべき情報は多くあります。
本記事では、白内障における片目・両目の手術費用の相場から、保険適用の条件、補助制度の使い方までわかりやすく解説します。
目次
白内障手術の費用はどのくらい?|相場と目安を解説

白内障手術の費用は、手術内容や施設の種類によって異なります。
まずは全体の費用感と、どのような条件で差が生まれるのかを理解することが大切です。
片目・両目の費用はどう違う?
通常、白内障手術は片目ずつ行われます。
片目ごとに費用が発生するため、両目を手術する場合は基本的に2回分になります。
健康保険が適用される一般的な単焦点レンズによる手術であれば、3割負担で片目あたり5~6万円、両目でおよそ10万円前後が目安です。
一方で、自由診療の多焦点レンズなどを選ぶと、片目で30万円〜60万円かかることもあります。
費用を抑えたい場合は、それぞれのレンズは機能も目的も違いますので、費用だけでなく、ご自身のニーズを慎重に考えてレンズの種類や病院の診療形態を慎重に検討しましょう。
入院の有無で費用は変わる?
近年、白内障手術は日帰りが主流です。
ただし、患者の体調や他の病気の有無によっては入院が必要となるケースもあります。
日帰り手術は入院費がかからないため、全体の費用は比較的抑えられます。
一方、入院が必要なケースでは、1泊あたり数千〜1万円程度の入院費が上乗せになる可能性があります。
また、入院日数が長くなれば、食事代や室料差額なども増えていきます。
費用を重視する場合は、手術前に必ず医師と日帰り手術が可能か相談しておきましょう。
費用の内訳とは?診察・検査・手術・薬代まで
白内障手術にかかる費用は、手術だけではありません。
事前の診察や検査、術後の診療、そして使用する目薬や飲み薬も含まれます。
具体的には、手術前に初診料・再診料の他視力や眼圧、眼底などを調べる各種検査が行われます。
手術当日は、局所麻酔や点眼麻酔の処置費用、レンズの材料費、手技料が発生します。
手術後も、一般的に感染症予防や炎症を抑える目薬が処方されます。
これらすべてを合計すると、保険診療の場合でも片目あたり5~6万円前後、自由診療の場合は30〜60万円程度となります。
最終的な総額を把握するには、事前に病院から見積りをもらい、内訳を確認しておくと安心です。
保険診療と自由診療の違いとは?

白内障手術には、健康保険が使える「保険診療」と、全額自己負担となる「自由診療」の2つの選択肢があります。
この違いを理解することで、費用面だけでなく手術内容やレンズ選びにも納得して判断できるようになります。
健康保険が適用される手術と条件
白内障手術で健康保険が適用されるのは、視力低下などの症状があり、医師が治療の必要性を認めた場合ですが、自覚症状があって受診される場合は、殆どがこのケースになります。
多くの場合使用される単焦点レンズは、保険適用対象となっています。
保険診療では、70歳未満は3割負担、70歳以上は1〜2割負担となることが多く、費用は抑えられます。
また、検査や術後の診療、点眼薬なども健康保険の対象に含まれるため、総額で見ても安心感があります。
ただし、視力が保たれており日常生活に支障がない場合は、医療上の必要性がないと判断され、保険対象外となることもあります。
手術を希望する場合は、事前に医師に保険適用の可否を確認しておくことが大切です。
自由診療の費用相場と特徴
自由診療は、保険が使えない代わりに最新の医療技術や高機能なレンズを選べるメリットがあります。
特に多焦点レンズは、遠くと近くの両方にピントを合わせやすいため、メガネを使わずに生活したい人におすすめです。
費用は片目で30〜60万円前後、病院によってさらに高額になることもあります。
自由診療は全額自己負担となるため、費用面においては勿論負担は大きくなります。慎重な判断が求められます。
その一方で、診療時間が柔軟だったり、手術設備が先進的であったりと、サービス面において満足度が高いケースも見られます。
視力の質や眼鏡依存度の軽減を重視したい方は、一つの選択肢として検討してみてください。
選定療養と自由診療の境界線に注意
白内障手術には、「選定療養」と呼ばれる中間的な制度が存在します。
選定療養とは、保険適用される治療を受けながら、希望に応じ自費で特別な医療を追加できる方法を指します。
たとえば、通常の手術は保険適用とし、レンズ部分のみグレードアップして自己負担にする、といった仕組みです。
この場合、術後の診察や薬代などが保険でカバーされるため、全額自由診療よりも費用負担を抑えられる可能性があります。
ただし、すべての医療機関が選定療養に対応しているわけではありませんし、眼内レンズの種類によっても異なります。
事前に対応可否を確認し、医師の説明を受けてから選ぶことが安心につながります。
白内障はレンズの種類で費用が変わる

白内障手術で使う人工レンズは、見え方だけでなく費用にも大きな違いがあります。
どのレンズを選ぶかによって、手術後の生活の質だけではなく、負担する費用が大きく変わってくるため、慎重に検討する必要があります。
この章では、代表的な人工レンズの種類と、それぞれの見え方や費用について詳しく解説していきます。
単焦点レンズ(保険適用)とは?
単焦点レンズは、遠くまたは近くのどちらか一方に焦点を合わせるタイプのレンズです。
国内の白内障手術で最も多く使用されており、健康保険が適用されます。
片目の自己負担は3割で約5万円前後が目安です。
ただし、焦点が一箇所にしか合わないため、手術後も遠近どちらかにはメガネが必要になるケースが殆どです。
このレンズのメリットは、構造がシンプルで光のロスや滲みが少なく、術後の見え方が安定しやすい点です。
術後に眼鏡の使用をしても構わない方、費用を抑えたい方におすすめです。
多焦点レンズ(自由診療)の費用と特徴
多焦点レンズは、遠近両方が見えるように設計された高機能レンズです。
複数の焦点を持ち、術後にメガネの使用頻度を減らしたい方に選ばれています。
しかし、このタイプのレンズは保険の適用外となり、選定療養又は自由診療として扱われます。
費用は片目あたり30〜60万円程度が一般的で、病院によってそれ以上になる場合もあります。
費用は高くなりますが、術後の生活の快適さや利便性を重視する方にとっては、大きなメリットがあります。
自分のライフスタイルに合った選択ができるよう、医師としっかり相談することが大切です。
レンズ選びで後悔しないためのポイント
レンズ選びは、費用だけでなく日常生活にも影響します。
そのため、手術前にライフスタイルや仕事の内容、趣味なども踏まえて判断することが重要です。
例えば、読書や手芸など近くを見る機会が多い方は、近方に焦点を合わせた単焦点レンズを選び、遠くを見るときはメガネを使うという選択肢もあります。
一方で、デスクワークも多いけれど、日常的に車の運転やスポーツをすることも多い人は、多焦点レンズによる眼鏡不要の生活が向いているでしょう。
手術後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、事前に十分な説明を受け、自分の希望と医師の判断をすり合わせることが不可欠です。
費用面だけでなく、術後の見え方や生活のしやすさを考慮して選ぶようにしましょう。
白内障手術の負担費用を公的制度で軽くする方法

白内障手術は医療費がかかる治療ですが、公的な制度をうまく活用すれば、自己負担を大きく減らすことができます。
特に高齢者や家計に余裕のない方にとって、事前に支援制度を知っておくことが重要です。
高額療養費制度の仕組みと申請方法
高額療養費制度とは、1か月間に支払った医療費が一定の上限を超えた場合、その超過分が払い戻される制度です。
たとえば70歳以上の年金暮らしの方であれば、自己負担の上限は1万2,000円前後になることもあります。
対象は保険診療の範囲に限られますが、手術費・入院費・検査費などが含まれます。
この制度を活用する場合、病院の窓口で「限度額適用認定証」を事前に申請しておくことがおすすめです。
そうすれば支払い時点で上限額が適用されるため、一時的に高額な医療費を立て替える必要がなくなります。
申請は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽや市町村の国民健康保険など)に行う必要があります。
入院が必要な方や両目手術を受ける方は、ぜひ活用をご検討してみてはいかがでしょうか?
医療費控除で戻るお金はいくら?
医療費控除は、年間の医療費が一定額を超えた場合、確定申告を通じて所得税の一部が還付される仕組みです。
対象となるのは、1世帯あたり年間10万円、もしくは所得の5%を超えた医療費です。
白内障手術の費用はこの基準を超えることが多く、控除の対象となる可能性があります。
保険適用の治療はもちろん、自由診療の費用や通院にかかった交通費(公共交通機関の利用)なども含まれます。
還付される金額は所得や支払った税金によって異なりますが、数万円単位で戻ってくるケースも少なくないので、領収書をきちんと保管し、確定申告時に忘れずに手続きを行いましょう。
自治体の独自補助制度が使えるケースも
一部の自治体では、高齢者や低所得者を対象とした医療費助成制度を独自に実施しています。
たとえば後期高齢者医療制度による助成や、高齢者医療費の一部助成などが挙げられます。
また、障害認定を受けている場合には、障害者医療費助成の対象になることもあります。
地域によって制度の名称や条件は異なりますので、役所や保健所に問い合わせて最新の情報を確認しておくと安心です。
手術を受ける前に補助制度を把握しておけば、必要な書類を揃えやすく、スムーズに申請できます。
家計に不安のある方は、医療機関だけでなく行政窓口にも一度相談してみることをおすすめします。
白内障手術の費用を左右する病院・手術方式の違い

白内障手術の費用は、レンズの種類や診療形態だけでなく、手術を受ける病院や手術方式によっても変わってきます。
納得できる手術を受けるためにも、これらの違いを理解しましょう。
大学病院・専門クリニック・眼科医院の違い
白内障手術は、大学病院、専門クリニック、地域の眼科医院など、さまざまな医療機関で受けることができます。
大学病院では多くの専門分野の医師がいるため、全身状態のあまり良くない方や他の疾患を合併しているケースでは安心な反面、検査や待機期間が長くなることがあります。
新しい機器や眼内レンズの採用には、病院全体の稟議が必要なので、導入が遅く、それらの運用に時間が掛かる傾向にあります。
一方、専門クリニックは白内障に特化し、そのために設計された施設で、白内障手術に関して最新設備を活用した短時間での施術が特徴的です。
また、地域の眼科医院では、親身な対応や通いやすさがメリットであり、費用も、入院で行われる病院よりも抑えられているケースが多くみられます。
また、自由診療をはじめとした、最新の眼内レンズも、導入が早いのも、泊なしよう手術専門のクリニックの特徴です。
日帰り手術vs入院手術のコスト比較
白内障手術は日帰りで実施できることが多く、費用を抑えたい方におすすめです。
外来での手術であれば、入院費や食事代、室料の負担が不要となるため、自己負担率が3割なら片目5~6万円で済むケースが多いです。
自己負担率が1~2割なら、更に低くなります。
ただし、全身の健康状態によっては医師が入院を勧める場合も考えられます。
入院になると1泊あたり数千〜1万円程度の入院費が追加され、トータルで7万円以上になることもあります。
手術方式は患者の希望や体の状態に応じて決まるため、費用だけでなく安全性を優先し、ご家族とも相談して選択することがが必要です。
複数の選択肢を提示してくれる医療機関を選ぶと安心できるでしょう。
最新手術機器や追加オプション費用に注意
少し前から、フェムトセカンドレーザーと呼ばれるレーザー白内障手術を行う施設も出てきています。
今のところ、従来の方法と比べて手術成績に大きな差は認められていませんが、これは自由診療に分類され、殆どが、多焦点眼内レンズの手術と組み合わされており、希望する場合は追加費用が発生します。
たとえば、フェムトセカンドレーザーによる手術を選ぶと、片目あたり5〜10万円の追加費用が必要になることがあります。
また、術後の視力回復を高める検査やオーダーメイドレンズなども、別途費用がかかる場合があります。
こうしたオプションはすべての患者に必要というわけではありません。
費用対効果を見極めたうえで、自分にとって本当に必要な内容かを医師と相談しながら決めましょう。
まとめ
白内障手術の費用は、保険診療か自由診療か、選ぶレンズの種類、手術を受ける病院によって大きく変わります。
高額療養費制度や医療費控除などの公的支援も活用すれば、自己負担を軽減できますので、費用面に不安がある方は、納得のいく選択ができるように事前にしっかり情報を集めましょう。